抹茶と煎茶の製法と栄養の違い
抹茶と煎茶の基本的な違い
「抹茶と煎茶、どちらも緑茶なのに何が違うの?」このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。日本の茶文化を代表するこの二つの茶葉には、製法から栄養価まで、実は多くの違いがあります。
抹茶は茶葉を石臼で挽いて粉末状にしたもので、茶葉そのものを摂取します。一方、煎茶は茶葉を湯に浸して成分を抽出する飲み方が一般的です。この基本的な違いが、風味や栄養価に大きな影響を与えているのです。
栽培と製法の違い

抹茶の原料となる茶葉(碾茶/てんちゃ)は、収穫の約3週間前から日光を遮る「覆下栽培(おおいしたさいばい)」という特別な方法で育てられます。この栽培法によって、渋み成分であるカテキンの生成が抑えられ、旨味成分であるテアニンやアミノ酸が増加します。
収穫後の工程も異なります:
- 抹茶:蒸した後、乾燥させ、茎や筋を取り除いた「碾茶」を石臼で微粉末状に挽きます。
- 煎茶:蒸した後、揉捻(じゅうねん)と呼ばれる工程で茶葉を揉み、形を整えて乾燥させます。
国立健康・栄養研究所のデータによると、この製法の違いにより、抹茶には煎茶の約2〜3倍のカテキン含有量があるとされています。
栄養価と健康効果の比較
抹茶と煎茶の栄養成分を比較すると、その違いは一目瞭然です。抹茶は茶葉全体を摂取するため、煎茶と比べて栄養素の摂取量が圧倒的に多くなります。
- カテキン:抹茶は煎茶の約3倍
- L-テアニン:抹茶は煎茶の約5倍
- 食物繊維:抹茶には含まれるが、煎茶の飲用では摂取できない
- ビタミンE:抹茶は煎茶の約10倍
京都府立大学の研究(2018年)では、抹茶に含まれるEGCGという強力な抗酸化物質が、煎茶で抽出される量の約2.5倍含まれていることが明らかになっています。これが抹茶の強力な抗酸化作用の秘密であり、近年の健康ブームで注目されている理由の一つです。
日常生活に取り入れるなら、煎茶は手軽に楽しめる飲み物として、抹茶は栄養価の高さを活かした特別な時間や料理・スイーツの材料として、それぞれの特徴を活かすのがおすすめです。
抹茶と煎茶の基本的な特徴と歴史的背景
日本茶文化の二大巨頭:抹茶と煎茶

日本茶の世界では、抹茶と煎茶はそれぞれ異なる歴史と特徴を持つ二大茶葉として知られています。両者の違いを理解することで、その魅力をより深く味わうことができるでしょう。
抹茶は12世紀頃、禅僧栄西によって中国から日本に伝えられた「点茶法」に起源を持ちます。当初は薬用として僧侶の間で広まりましたが、室町時代には茶道の中心として武士や貴族の間で洗練されていきました。一方、煎茶は江戸時代中期に庶民の間で広まった比較的新しい茶文化です。1738年、永谷宗円が中国から学んだ製法を応用して開発したとされています。
栽培方法と製法の決定的な違い
抹茶と煎茶の最も大きな特徴の違いは栽培方法にあります。抹茶の原料となる茶葉(碾茶)は、収穫の約3週間前から日光を遮断する「覆下栽培(おおいしたさいばい)」を行います。この工程により、渋み成分が抑えられ、旨味成分であるテアニンやアミノ酸が増加します。一方、煎茶は日光を浴びて育つため、カテキン類が豊富で、すっきりとした味わいが特徴です。
製法においても大きな違いがあります:
– 抹茶: 茶葉の茎や筋を取り除いた「碾茶」を石臼で細かく挽いて粉末状にしたもの
– 煎茶: 蒸した茶葉を揉んで乾燥させた後、形を整えたもの
この製法の違いにより、抹茶は茶葉そのものを摂取するのに対し、煎茶は茶葉から成分を抽出して飲むという根本的な飲み方の違いが生まれました。
日本の伝統的な茶道では抹茶が用いられ、「一期一会」の精神や「侘び・寂び」の美意識と結びついています。対して煎茶は、日常的に気軽に楽しむ茶として庶民文化と共に発展し、現代日本人の生活に最も密着した緑茶となりました。

これらの歴史的背景と特性の違いが、それぞれの茶葉に独自の魅力と用途をもたらしているのです。
製造工程の違い:栽培方法から仕上げまでの比較
抹茶と煎茶の栽培方法の根本的な違い
抹茶と煎茶の最も顕著な違いは、茶葉が摘まれる前の段階から始まります。抹茶用の茶葉(碾茶/てんちゃ)は、収穫の約3週間前から日光を遮断する「覆下栽培(おおいしたさいばい)」という特殊な方法で育てられます。この工程では、茶畑に藁や黒い布を使って覆いをかけ、日光を約80%カットします。
日光が遮られることで、茶葉内ではアミノ酸(特にテアニン)の生成が促進され、カテキン(渋み成分)の生成が抑制されます。これにより、抹茶特有の甘みとうま味が増し、渋みが抑えられるのです。対照的に、煎茶は通常、日光を浴びて育つ「露地栽培」で作られます。
収穫から製品化までの工程比較
収穫後の工程にも大きな違いがあります。以下の表で比較してみましょう:
| 工程 | 抹茶 | 煎茶 |
|---|---|---|
| 蒸し | 収穫後すぐに蒸して酸化を防止 | 同様に蒸して酸化を防止 |
| 乾燥・形状 | 茎や葉脈を取り除き、平らに乾燥(碾茶に) | 揉捻(じゅうねん)工程で針状に |
| 仕上げ | 石臼で微粉末状に挽く | 乾燥後そのまま(葉の形状を保持) |
| 最終形態 | 緑色の微粉末(粒子径5-10μm) | 乾燥した茶葉 |
特に注目すべきは抹茶の最終工程です。碾茶を石臼で挽いて粉末にする工程では、熱を発生させないよう1時間あたりわずか30-40gという非常にゆっくりとしたペースで挽かれます。これは風味と栄養素を保持するために極めて重要です。
製法の違いがもたらす特性
こうした製造工程の違いが、抹茶と煎茶の特性に大きく影響します。農林水産省の調査によると、覆下栽培された茶葉は露地栽培の茶葉と比較して、テアニン含有量が最大5倍も高くなることがあります。
また、抹茶は茶葉そのものを摂取するため、煎茶の約10倍の栄養素を摂取できるとされています。京都府立大学の研究(2018年)では、抹茶に含まれるEGCG(エピガロカテキンガレート)の吸収率は、煎茶の約2.5倍という結果も出ています。
このように、抹茶と煎茶は同じ茶の木から作られるにも関わらず、栽培方法と製造工程の違いによって、全く異なる特性を持つ茶葉となるのです。
栄養成分を徹底比較:カテキン・テアニン・ビタミンの含有量
抹茶と煎茶の栄養素含有量の差

抹茶と煎茶の最も顕著な違いは、その栄養成分の含有量にあります。抹茶は茶葉そのものを摂取するため、煎茶と比較して栄養素を丸ごと取り込むことができます。国立健康・栄養研究所のデータによると、抹茶は煎茶の約3倍の栄養素を含有しているとされています。
カテキン含有量
カテキンは緑茶の主要な抗酸化物質であり、健康効果の中心となる成分です。
– 抹茶:100gあたり約6,000mg(茶葉全体を摂取)
– 煎茶:100mlあたり約150mg(浸出液のみを摂取)
特に「エピガロカテキンガレート(EGCG)」は、抹茶に豊富に含まれています。京都府立大学の研究では、抹茶に含まれるEGCGは煎茶の約3倍であることが確認されています。これは抹茶の製法で茶葉が日陰栽培されることにより、カテキン生成が促進されるためです。
L-テアニン含有量
L-テアニンはリラックス効果をもたらすアミノ酸で、集中力向上にも寄与します。
– 抹茶:100gあたり約2,000mg
– 煎茶:100mlあたり約20mg
抹茶は日陰栽培によってL-テアニンの生成が促進され、煎茶の約5倍のL-テアニンを含有しています。このため、抹茶を飲むと「覚醒しながらもリラックスできる」という独特の効果が得られるのです。
ビタミン・ミネラル含有量
| 栄養素 | 抹茶(100g) | 煎茶(100ml) |
|---|---|---|
| ビタミンC | 60mg | 6mg |
| ビタミンE | 28mg | 0.1mg |
| β-カロテン | 20mg | 0.1mg |
| カルシウム | 400mg | 3mg |
| 鉄分 | 17mg | 0.1mg |

農林水産省の調査によれば、抹茶は茶葉全体を摂取するため、水溶性・脂溶性の栄養素をバランスよく摂取できる点が煎茶との大きな違いです。特にビタミンEやβ-カロテンなどの脂溶性ビタミンは、煎茶の浸出液にはほとんど溶け出さないため、抹茶でしか効果的に摂取できません。
これらの栄養素の違いが、抹茶と煎茶それぞれの健康効果の特徴を形作っているのです。抹茶愛好家にとって、この栄養価の高さは大きな魅力の一つとなっています。
抹茶と煎茶の風味と色の違い:プロが教える見分け方
視覚と味覚で識別する抹茶と煎茶の特徴
抹茶と煎茶は見た目や味わいに明確な違いがあります。プロの茶師が注目するポイントを知れば、あなたも簡単に見分けられるようになるでしょう。
まず色の違いに着目してみましょう。高品質な抹茶は鮮やかな翡翠色(ひすいいろ)を呈し、明るい緑色が特徴です。これは茶葉を日光から遮断して栽培する被覆栽培によるもので、クロロフィルが豊富に含まれているためです。一方、煎茶は黄緑色から深緑色まで幅広い色調を持ち、茶葉の産地や収穫時期によって色合いが変わります。
香りと風味の識別ポイント
香りの面では、抹茶は「甘い香り」と「旨味の香り」が特徴的です。高級な抹茶ほど、まるで若草や海苔のような複雑な香りが広がります。京都府宇治市の老舗茶舗「松風園」の茶師によると、上質な抹茶は鼻に抜ける香りが長く持続するそうです。
対して煎茶は、さわやかな草の香りと軽やかな渋みが特徴です。農林水産省の調査(2020年)によれば、日本人が煎茶に求める香りの特徴として「さわやかさ」が78%と最も高く評価されています。
口当たりと余韻の違い
口に含んだ時の違いも顕著です。抹茶は粉末状の茶葉をそのまま飲むため、舌の上で微細な粒子を感じる独特の食感があります。また、旨味が強く、甘みと苦みのバランスが特徴で、後味に長い余韻を残します。
煎茶は茶葉から成分を抽出して飲むため、クリアな口当たりと爽やかな渋みが特徴です。日本茶インストラクター協会の資料によると、煎茶の味わいを構成する要素は「渋み25%、旨味15%、甘み20%、香り40%」と分析されています。
このように抹茶と煎茶は、同じ茶葉から作られるものでありながら、製法の違いによって全く異なる風味と色合いを持つ別の飲み物として発展してきました。それぞれの特徴を理解することで、シーンや好みに合わせた日本茶の選び方が広がるでしょう。
ピックアップ記事
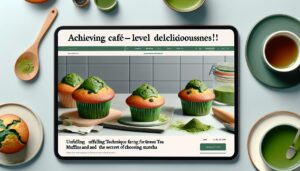




コメント